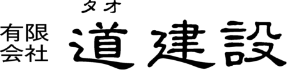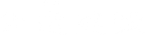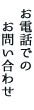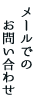1,耐震工事
記憶に新しい阪神淡路大震災や東日本大震災などの大地震の影響は、私たちの想像を遥かに超えるものでした。
今後、起こり得るといわれている南海トラフ地震などは広島にも影響があると考えられます。
今、既存木造住宅の耐震診断・補強の推進に対する声が高まっている中で、そういった大地震への備えを皆さんはどうお考えでしょうか。
地震に対する建築的手法として耐震・制震・免震というものがありますが、耐震は地震に耐える。制震は地震の力を減衰させる装置に備える。免震は地震の力そのものを地盤との境で遮断するという考え方になります。
住宅にとっては、耐震、制震の手法をとることで、安心安全な住まいへと変えることが出来ます。
弊社ではこれからご紹介する手法でより良い家造りをご提案させて頂きます。
尚、道建設では耐震工事を行うにあたり、耐震改修促進法に則り、専用のプログラムを用い耐震診断を行い、耐震改修計画を作成し数値化した分かりやすい説明をしております。
耐震工事の流れ
耐震診断
屋根裏や床下等にもぐり、構造上支障のある被害・劣化はないか確認を行います。
耐震設計
様々な補強方法がある中で、構造計算上最適なものや、ローコストとなるように無駄のない施工が行えるものなどを選択し、計画・設計を行います。
補強工事
全面的な改装の時や表面的な改装の時など、様々な施工条件に合った方法で対応いたします。住みながらのリフォームの場合も工程を管理しながら、耐震設計により計画した施工方法で無駄が無く安全な施工を行います。
注意すべき点(確認してみてください。)
- 比較的古い建物(昭和56年5月以前)に建てられた建物ですか?
- 今までに大きな災害に見舞われたことはありますか?
- 増築を行っている場合に、必要な手続きを行っていますか?
- 竣工後20年以上経過しているが、修繕を全く行っていないという建物ではないですか?
- Lの字や、Tの字などの複雑な平面形状の建物ではないですか?
- 1辺が4m以上の吹抜けはありませんか?
- 2階建て以上の場合、2階外壁の直下に1階の内壁または外壁が見当たらないことはないですか?
- 1階外壁の東西南北各面のうち、壁が全く無い面はないですか?
- 和瓦、洋瓦など比較的重い屋根葺き材で、1階に壁が少ないということはないですか?
- 「鉄筋コンクリートの布基礎またはべた基礎・杭基礎」以外の基礎によって家が支えられていませんか?
以上に1点でも当てはまる住宅は診断を推奨します。
2,耐震診断法
在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁構法の住宅(3階建以下、500㎡以下)
診断方法には、一般診断法と精密診断法というものがあります。
お住まいの診断を行うにあたって、精密診断を行うためには家の各箇所を破壊して調査する必要があり、破壊した場合は当然ながら復旧の費用もかかってしまいます。
破壊調査を行わず、精密診断を目視のみで行うとすると構造体内部の劣化が判定できず、結果として一般診断に比べて診断の精度が落ちてしまう可能性があります。
それに比べ一般診断法では、精密診断を行う場合に考えられる構造体の劣化等をあらかじめ織り込んだ診断となっています。
詳細な検討を建物のすべての部位では行わず、代表的な部位で平均的な評価を行うこととなります。
そのため、家の各箇所を破壊して診断を行う精密診断に比べ、正確さでは一歩譲るものの、破壊調査なども行わないためより安価な診断結果を出すことが出来ます。
よって弊社では一般診断法を採用しています。
耐震工事の流れ
目的として、耐震補強の必要性の有無を判定します。
診断は建築関係者が行い、非破壊による調査でわかる範囲の情報に基づくもので判定する方法です。極めてまれに(数百年に一度)発生する地震動による倒壊の可能性の有無について実施する。
対象とする住宅の工法によって、2つの方法があります。
- 方法1
- 壁を主な耐震要素とした住宅を主な対象とする。
- 方法2
- 震要素とする伝統構法で建てられた住宅を対象とする。主要柱径140mm以上
診断項目
診断は、(a)地盤・基礎、(b)上部構造の大きく2つの項目に分けられます。
- (a)地盤・基礎
- 地盤・基礎は、上部構造の評価に含まれないが、地震時に注意すべき点を注意事項として指摘します。
- (b)上部構造
- 上部構造は、建物の耐震性能を評価するもので、「強さ」、「耐力要素の配置等による低減係数」、「劣化度による低減係数」の3項目からなっています。
これら全ての項目を診断し、評点を算出、それらを掛け合わせることにより上部構造評点を算出します。
(a)(b)の結果から、診断建物の(c)総合評価が行われます。
耐力の診断
上部構造の耐力の診断は、当該住宅が保有すべき必要耐力と実際に保有している耐力を比較することでおこないます。
総合評価
(a)地盤・基礎:地震時におきる被害について注意事項を記述する。
(b)上部構造
3,耐震補強
- 地盤、基礎の耐震補強では、上部構造の耐震要素が設計上の性能を発揮でき、建物が受けた地震力を伝えられるだけの性能を確保します。
- 軟弱地盤の場合、建物の振動が大きくなるため、十分な壁量を確保するとともに鉄筋コンクリート造のべた基礎や布基礎を用いるなどの配慮が必要となります。
- 地盤の悪い場所では、地震時の性能が上部構造で確保されていたとしても、時間の経過と共に不同沈下が起こり、建物が傾斜する場合があります。そのような地盤においては、日常の生活に支障をきたさぬよう、地盤改良が必要な場合があります。
- ひび割れのある鉄筋コンクリート造の基礎や無筋コンクリート造の基礎の耐震補強
- 1.ひび割れの補修を行う。
- 2.無筋コンクリート造の基礎は、鉄筋コンクリートの布基礎と抱合わせることで補強を行う。
- 3.無筋コンクリート増では局所的に強い壁を用いず、耐震要素をバランスよく配置する。
- その他基礎として、玉石、石積、ブロック積の場合は、足固めを行い、建物との一体化を図る。
- 上部構造の耐震補強では、壁の耐力、独立柱といった耐震要素を必要量確保すると共に耐震要素の配置等の低減を出来るだけ少なくします。
- 壁、垂れ壁、腰壁つき独立柱といった耐震要素を必要量確保し、本来の構造性能を発揮できるように壁の周辺部材・接合部の補強、劣化の補修等を行います。
- 建物のねじれ振動を起こさないように耐震要素をバランスよく配置する。
- 建物の形状が平面的、立面的に整形でない場合には、耐震要素を増やし、床面の剛性・耐力を確保します。
- 2階の耐震要素で直下に柱が無い場合には、耐震要素を支える梁の曲げ剛性、耐力を確保します。
- 劣化
劣化している部位は交換するとともに、交換部材と既存部材の接合部を補強します。
併せて、劣化の原因を取り除くことが重要となります。(防蟻対策) - その他補強計画
瓦や外壁の脱落、ブロック塀の崩壊がないように、十分な止め付けやブロック塀では控え壁をつけるなどの地震対策が必要となります。
また、耐震要素を増やすことが出来ない場合には、屋根の軽量化など、建物の重量を減らすことによって耐震性を向上させることが出来ます。
補強方法
耐震診断により、現状の耐震性能を検討し、必要な耐震補強を行う上で、全面改装工事・部分改装工事それぞれに適した方法・補強部材を選択します。
補強部材色々
 鋼製ブレース
鋼製ブレース 木製ブレース
木製ブレース 制振ダンパー
制振ダンパー 耐震パネル
耐震パネル 抱合せ基礎補強
抱合せ基礎補強  アラミド繊維基礎補強
アラミド繊維基礎補強